川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)
東武東上線新河岸駅西口から徒歩1分の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。
TEL.049-246-0200
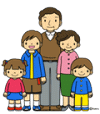
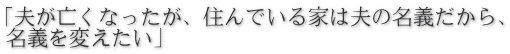
![]()
1.相続登記
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ヶ月以内)のよ
うに、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
長期間放っておいたとしても罰則もありません。
![]() 令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
(ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、登記されてないものは
義務化の対象になります。)
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万以下の過料が科される可能性が
あります。
また、相続登記や遺産分割協議をしないで長期間放っておくと以下のような不都
合が生じる恐れがあります。早めに相続登記を済ませた方が良いでしょう。
1.相続登記に必要な書類が取得できなくなる
相続登記の必要書類の中には、法律で保存期限が定められているものがあります。
例えば住民票の除票や戸籍の附票は死亡後5年、除籍謄本は除籍後150年経つ
と廃棄されます。
相続登記を申請する際、別途様々な証明書が必要になりかえって費用と手間がか
かってしまいます。
2.相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になる
長期間遺産分割協議をしないで放っておくと、協議を行うはずだった相続人が亡く
なり、さらにその相続人の配偶者や子供へ相続権が移っていきます。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と長男の二人で、母親が自宅を相続した
い場合、何年も遺産分割協議をしないで放っておいて、長男が結婚した後に亡く
なってしまった場合、自宅の相続権を長男の妻が持つことになります。
遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、お金を要求されたり、話し合い
に応じてくれない場合もあります。
3.相続人が高齢になると、遺産分割協議が行いにくくなる
相続人のうちのどなたかが高齢になり、認知症等で判断能力が低下すると、家庭
裁判所に申し立てて、認知症になった相続人の代わりに代理人=成年後見人を選任
してもらう必要があります。成年後見人を選任するには、相当な費用と数ヶ月の期
間がかかります。
4.不動産の一部が他人に差し押さえられてしまう恐れがある
遺産分割協議を行っていない場合、相続人は法律上の相続分どおり相続している
ものとみなされます。他の相続人が勝手に法定相続分どおりの持分で相続登記を
行うことも可能ですまた、相続人の一人の債権者が、勝手に不動産の相続登記を代
位で行い、その相続人の持分だけを差し押さえることも認められています。
5.不動産を売却したり担保に入れることができなくなる
上記1~4の理由で、相続登記をしていない場合、不動産を売却したり、お金の
借入等で担保に提供することができません。いざお金が必要になった時に現金化で
きないという不都合が生じます。
6.火災保険の更新や防音工事等の補助金申請ができなくなる
火災保険の更新をする際、相続登記(不動産の名義変更)を要求してくる保険会社
もあります。また防音工事の補助金申請を行う際も名義が変わっていないと認可が
下りません。
2.相続登記手続の流れ
①相続の発生
↓
②遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続、必要書類が違って
きます。公証役場で公正証書遺言検索システムを利用すると便利です。
自筆証書遺言がある場合、遺言書検認の手続を行います。
↓
③相続人・相続財産の調査
遺言書がない場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類を取得
して誰が相続人となるかを調査します。
また、不動産に関して土地建物の権利証、名寄帳等で相続登記をする物件にもれが
ないか確認します。
名義書換の必要な預貯金・株式などの遺産もリストアップします。
↓
④遺産分割協議と協議書の作成
誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議し、協議が整いましたら
その 内容に従い、協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をします。
尚民法に定められた相続分で登記をする場合は、協議書は不要です。
↓
⑤登記申請
全ての書類が揃いましたら、法務局へ登記申請します。
当事務所ではオンライン申請の方法にて申請しますので、全国どこの法務局でも対
応可能です。
↓
⑥登記の完了
3.相続登記に必要な書類
・遺言書がない場合
1. 被相続人(死亡した人)の生まれた時から死亡した時までの戸籍謄本、
除籍謄本、改製原戸籍
死亡時の本籍地及び従前の本籍地等で取得できます。
尚、法改正により本籍地以外の市区町村の窓口でも取得出来るようになりました。
2. 被相続人が登記簿上の所有者と一致していることを証する書面
通常は、被相続人の除住民票もしくは戸籍の附票です。
尚一致しない場合は、不在籍・不在住証明書になります。
3. 法定相続人全員の(1)戸籍抄本又は謄本
(2)住民票 ※不動産を取得される方のみで結構です。
4. 民法上の法定相続の持分によらない遺産の分け方をした場合は、遺産分割協議書(法定相続人全員で署名及び実印の押印が必要)及び相続人全員の印鑑証明書
5. 固定資産評価証明書
市町村役場、都税事務所で取得できます。
6. ご本人確認書類
例)運転免許証、パスポート、健康保険証、住基カード等
・遺言書がある場合
1. 被相続人(死亡した人)の死亡した時の戸籍謄本、除籍謄本
死亡時の本籍地で取得できます。
尚、法改正により本籍地以外の市区町村の窓口でも取得出来るようになりました。
2. 被相続人が登記簿上の所有者と一致していることを証する書面
通常は、被相続人の除住民票もしくは戸籍の附票です。
尚一致しない場合は、不在籍・不在住証明書になります。
3. 不動産を相続する方の(1)戸籍抄本又は謄本
(2)住民票
4.固定資産評価証明書
市町村役場、都税事務所で取得できます。
5.遺言書
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言の場合は検認不要です。
6. ご本人確認書類
例)運転免許証、パスポート、健康保険証、住基カード等
- 戸籍謄本又は抄本は同一在籍の場合、重複して必要はありません。
- 住民票は同一居住の場合、重複して必要はありません。
- 相続を証する書面は、手続き終了後お返し致します。
- その他必要な書類は、ケースにより多少異なります。
4.相続登記の費用
相続登記手続費用
| 業務内容 |
報酬
|
登録免許税等実費
|
解説
|
|---|---|---|---|
| 相続登記申請 |
38,000円~
|
固定資産評価額×0.4% | 不動産の価格及び筆数等により異なります。 |
| 遺産分割協議書作成 |
10.000円~
|
0円 | 遺産に不動産がある場合 |
| 相続関係説明図作成 | 5,000円~ | 0円 | |
| 戸籍謄本等取得(1通) | 2,000円 |
200~750円
|
|
| 登記簿謄本取得(1通) | 500円 |
600円
|
|
|
法定相続情報一覧図作成 |
20,000円~ | 0円 | ・相続人の数、数次相続及び代 襲相続等の事案に応じて算出 させて頂きます。 ・相続登記手続きをご依頼頂き 相続登記との同時申請が可能 の場合は金10,000円となります |
その他の相続関連業務
| 業務内容 |
報酬
|
実費
|
解説
|
|---|---|---|---|
| 特別代理人選任審判書 |
30,000円~
|
1,160円
|
郵送料・必要書類取得費用別途 |
| 遺言書検認申立書作成 |
30,000円~
|
約1,000円
|
郵送料・必要書類取得費用別途 |
| 不在者財産管理人選任 |
30,000円~
|
約1,000円
|
郵送料・必要書類取得費用別途 |
| 相続財産管理人選任 |
30,000円~
|
約1,000円
|
郵送料・必要書類取得費用別途 |
| 相続放棄申述書作成 |
30,000円~
|
1,250円
|
郵送料・必要書類取得費用別途、2人目以降報酬10,000円引き |
| 日当 | 5,000円~ | 埼玉県在住の方の場合は日当はいただいておりません |
